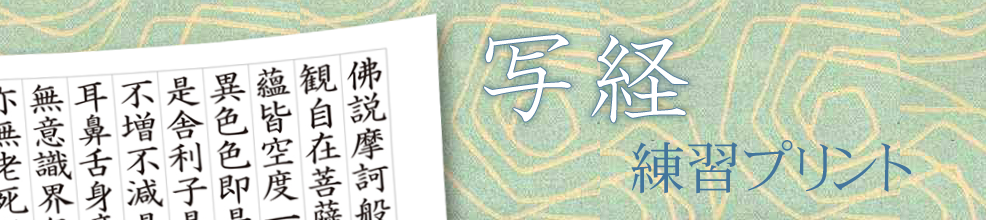写経は古くから仏道修行の方法としてもおこなわれてきました。お手本となる「お経」は、お釈迦様(紀元前5~4世紀ごろ)の教えを説いたもので、お釈迦様が亡くなられた後に弟子たちがその教えを後世に伝えようと文字に残しました。もともとお経はお釈迦様の生まれたインドの文語「サンスクリット語」で書かれていましたが、中国に仏教が伝わると中国の僧侶たちはインドに勉強に行き、お経を持ち帰ってきました。そして漢語に翻訳したのです。『西遊記』に登場する三蔵法師は、そのような僧侶の一人である「玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)」(602~664年)をモデルにしたと言われています。唐の時代には国家事業として写経がおこなわれ、書き写された経典は寺に安置されました。

日本に仏教が伝わったのは6世紀ごろで、多くの経典も伝わってきました。『日本書紀』には、天武天皇2年(673年)に奈良の川原寺で書生を集めて「一切経」を写させたのが日本で最初の写経である、という記録があります。天平時代には東大寺が建立され、国家鎮護のために仏教が重んじられます。奈良時代には仏教のテキストとして大量のお経が必要となり、国をあげての写経がおこなわれました。

平安時代後期には、『法華経』を中心とした装飾経が多く書写されたと言われています。装飾経は貴族などの発願によって制作された美麗な写経のことで、代表的なものに平清盛が厳島神社に奉納した『平家納経』があります。
鎌倉時代には、禅宗や浄土宗などが盛んになり、写経はあまりおこなわれなくなります。また、その後の時代には印刷技術の発達によって、写経は個人の信仰の一環として位置づけられるようになりました。
現代では、追善供養のほか、病気平癒や災厄を除けるなどの願い事のため、また、心の安定や字の上達のためなどさまざまな目的で写経がおこなわれています。